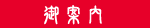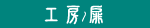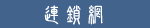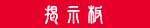| 『日本近代文学大事典』机上版(日本近代文学館 編 昭59.10 講談社)から「坂口安吾」の項目を抜粋しました。少し大袈裟で安吾を美化しすぎているきらいもありますが,安吾の生涯をひととおり知ることができます。
坂口安吾 さかぐちあんご 明治39.10.20〜昭和30.2.17(1906〜1955)小説家。新潟市西大畑町の生れ。本名は炳五。父仁一郎,母アサの五男で,13人兄妹中の12番目の子供である。生家の坂口家は代々阿賀野川流域の大安寺村に住した旧家で,「阿賀野川の流れが尽きても坂口家の富は尽きることがない」という意味の俚謡が残っているほどの大地主であった。しかし安吾が生れたころは父仁一郎が政治家として財を傾けたため,新潟市の家は大きく,多くの居候や使用人がたむろしていたが家計は火の車であった。安吾は幼いころから放任主義の父や,家計に疲れヒステリックな母になじまず(父仁一郎は五峰と号し,宰相らと親交を持つ越後きっての高潔な有力政治家で,漢詩人としても一家をなしていた),「家」のむなしさを知り嫌悪し,学校にも反逆し幼稚園,小学校,中学校を通じてあまり登校せず,餓鬼大将として悪戯のかぎりをつくす一方,ひとり日本海に面する浜辺に寝ころんで空と海と風と波と光と小石などを終日眺め,そこに透明なせつないふるさとを母を想った。後年の『石の思い』などにあらわれているように荒漠たる風と石は安吾文学の原風景,せつないふるさとといってよいだろう。
大正11年,教室の机に「余は偉大なる落伍者となって何時の日にか歴史の中によみがへるであらう」と彫って県立新潟中学を退学した安吾は,東京の豊山中学に編入学する。このころから文学と仏教に強い関心を抱きはじめた。12年18歳のとき,父の死にあい,14年中学卒業と同時に,代用教員として東京の下北沢にある分教場に勤め,自然の中に悪童たちと遊んだ。その体験は『風と光と二十の私と』に詳しい。しかしそのころから求道の厳しさにたいする憧れが強まり,仏教を勉強しようと15年東洋大学印度哲学科に入学した。悟りをひらこうと多くの哲学宗教書を読破,睡眠4時間という厳しい修行生活を1年半続け,神経衰弱に陥ったが,それを梵語,チベット語,パーリ語,フランス語などを猛然と勉強することにより克服した。とくにフランス語学習のため,アテネ・フランセに通い,モリエール,ヴォルテール,ボーマルシェなどを愛読,「賞(エロージュ)」をもらうほど,習熟した。中学時代の山口修三のほか,アテネ・フランセで長島萃,江口清,菱山修三,葛巻義敏らの文学好きの青年たちと交友を深めた。当時の坂口安吾は聖人をめざしての悟りへの求道生活と挫折感による自殺への誘惑,デカダンスの生活へのめりこもうという破戒僧的な衝動,霊肉の葛藤などに悩み,自信を喪失していたにもかかわらず,友人やまったく未知の人からもいかにも自信にあふれた人間のように見られ,深い思索と高貴な魂を持つ近寄りがたい存在として畏敬されていた。安吾に近づいた友人は圧倒的な影響をうけ,劣等感を抱き自殺したり破滅したりするものが多かった。おのれの才能や自負に生命を賭けた闘いの時期を安吾は「暗い青春」とふりかえって述べている。とくに長島萃との闘いは凄絶をきわめた。安吾はこの青春の試練についに勝抜いたが,長島萃の亡霊はながく安吾の中に宿ることになった。
昭和5年,江口,葛巻,山田らと「言葉」を創刊,翌6年1月の第2号に処女作『木枯の酒倉から』を発表,ついで「言葉」の後継同人誌,岩波書店発行の「青い馬」に『ふるさとに寄する讃歌』,6月に『風博士』,7月に『黒谷村』を発表した。『木枯の酒倉から』は,彼の原風景の風と石を象徴した作品,『風博士』も同じ原風景をもとにポーの『ボンボン』などに触発された徹底したファルス(笑劇)で,およそ日本の近代文学の伝統や常識にはずれたものであった。ところが牧野信一が「文芸春秋」の別冊で『風博士』を絶賛,ついで晦渋な『黒谷村』をも賞めた。無名の新人坂口安吾はにわかに注目され,同じ年の9月には「文芸春秋」に『海の霧』を発表,牧野信一主宰の「文科」に『竹藪の家』を連載する。6年,プロレタリア文学の新人以外,登場することがきわめて困難だった当時に,坂口安吾は異例の輝かしい芸術派の新人としてデビューした。『霓博士の頽廃』(「作品」昭6.10)『蝉』(「文芸春秋」昭7.2)『村のひと騒ぎ』(「三田文学」昭7.10)など意欲的な秀作を発表するが,7年の夏ごろ,新進女流作家の矢田津世子を知り,烈しいプラトニック・ラブに陥り,安吾は懊悩し,酒場のマダムなどと同棲するデカダンスな生活を重ね,4年後ようやく彼女と袂別を決意し,12年単身京都に移り,伏見の下宿に住む。矢田津世子との愛を清算し,半生の墓碑銘ともいうべき長編『吹雪物語』の執筆に専念する。この長編は故郷新潟を舞台に祖父の時代から現代までの家や血をめぐる利害葛藤,矢田津世子などとの恋愛をふくめた安吾の半生の体験などを,昭和初年に同時的に圧縮凝縮したアンチ・ロマンともいえる野心的な構想だが,完全な失敗作でただ雪国の暗い詩情だけが印象的だ。安吾は自分の才能のなさにはじめて絶望をおぼえ,どん底の淪落の生活を送る。
13年帰京,ついで取手,小田原などを転々と放浪し,孤独の涯に自己を置こうとした。しかしそういう中で『閑山』(「文体」昭14.12)『紫大納言』(「文体」15.2)『木々の精、谷の精』(「文芸」昭15.3)などの新境地をひらく佳品をおもに三好達治編集の「文体」に発表,切支丹はじめ古代や戦国の歴史文献を読み『島原の乱』の構想をたてたりする。太平洋戦争が開始されるとデカダンスの自分の生活に特攻隊の軍神をひきつけた『真珠』(「文芸」昭17.6)という佳編を書くとともに,国粋主義の時代,奈良や京都の寺や仏像は焼けてもよい,必要ならば法隆寺をこわして停車場にしても,日本人の生活が健康なら日本文化は続くと刑務所やドライアイス工場に必要の美を認めた。また家を,いや帰ることを否定し,救いのないところにこそ文学のせつない故郷を見いだそうとする,大胆な『日本文化私観』(昭18.12 文体社)を刊行する。
日本の崩壊という歴史的事件を目の当たり見ようとして空襲下の東京に残った安吾は,敗戦後の昏迷の中で,いちはやく戦後の本質を把握洞察した。そして昭和21年「新潮」の4月号に『堕落論』6月に『白痴』を発表する。この2編は,若者を中心に戦後虚脱していた日本人に衝撃を与えた。とくに『堕落論』の戦争下の無我の美しさをうたいしかしそれは死の美学であり,生きるためには人間は堕落せねばならぬ,堕ち切ることにより真実の救いを発見せよという訴えは,当時の若者たちにとって,戦前戦中の倫理観をいっさい否定し,戦後への主体的な生き方を教える革命的宣言として広く深い影響を与えた。『堕落論』によってはじめて自主的な戦後日本が開始されたといってよい。さらに『白痴』において,人間も家畜も区別ない原初的状況下,いっしょに逃げまわる白痴の女の肉体的,本能的なせつないかなしさを実存主義的発想で小説化し,戦後文学(第一次戦後派,第三の新人,さらには大江,開高らの現代文学にいたる)の突破口をつくった。ついで『外套と青空』(「中央公論」昭21.7)『女体』『恋をしに行く』と,従来の肉体を捨象した思想や観念にたいし,肉体自体が思考する,性の思想化ともいうべき作品を発表する。坂口安吾は,織田作之助,太宰治,石川淳とともに新戯作派,無頼派と呼ばれ,戦後乱世のオピニオン.リーダーとして,流行作家,評論家になる。『石の思ひ』(「光」昭21.11)『桜の森の満開の下』(「肉体」昭22.6)のごとき傑作を発表するとともに,梶三千代と結婚,その献身をかなしく描いた『青鬼の褌を洗う女』(昭22.10),戦後風俗をえぐった『金銭無情』などを書き,一方『道鏡』(「改造」昭22.1)『二流の人』『織田信長』など歴史小説,さらに『不連続殺人事件』(「日本小説」昭22.8〜23.8)などの推理小説にも挑戦する。22年2月から「東京新聞」に『花妖』を連載するが,難解のため中断させられる。
昭和24年2月,睡眠薬(アドルム)と覚醒剤と中毒症状が昂じ東大神経科に入院した。日常生活には凶暴的錯乱的行動がつづいたが,当時「群像」に連載していた『火』(にっぽん物語)はきわめて健康,明晰で錯乱の影もない。彼は奔放な精神と激情を,理性のもとに統一化しようと試み,その闘いの中に疲れ破れ,一時的に錯乱に陥ったといえよう。意志力によりそれを再統一した安吾は,『街はふるさと』を「読売新聞」に連載(昭25.5〜10)し,10月『明治開化 安吾捕物帖』を25年から27年と連載する。この「捕物帖」は勝海舟を登場させ,戦後文化と明治開化期の文化の軽薄さを批判し,土着の人間性を探ったすぐれた文明批評である。昭和25年1月「文芸春秋」に世相を斬る『安吾巷談』を連載,みずから講談師と称し,天皇制,共産党をはじめ戦後のタブーに挑戦し,独自の庶民的な文明論を展開する。いっさいの権力を認めない彼は28年国税局と税金滞納,差押えをめぐって『負ケラレマセン勝ツマデハ』(昭28.6)はじめの抗議文を発表,税金闘争をひとりたたかい抜き,同年10月には競輪不正事件で自転車振興会を相手どりたたかう。これらのたたかいは誰とも徒党を組まない孤独なたたかいであった。安吾が『堕落論』において人間は弱く堕ち切れないだろうと書いた予言のとおり,人々は経済復興,生活安定とともに堕ち切ることをやめ,時代と妥協し安吾を時代遅れの狂人として見捨てたのだ。しかし安吾はそういう中で,日本の古代史を研究し,天皇家が朝鮮系であること,朝鮮の歴史が日本に反映していることなどをいちはやく指摘した安吾独自の古代史を構想し,『安吾史譚』『安吾新日本地理』『安吾新日本風土記』などで卓抜な史観を展開した。
その間,飛騨の歴史的探索から『夜長姫と耳男』(「新潮」昭27.6)という傑作を,また戦国の研究から『信長』そして遺作となった秀吉晩年の心理をえぐった『狂人遺書』(「中央公論」昭30.1)などを書いている。
桐生の旧家に住み息子の綱雄(ママ ※正しくは綱男)も生れ,古代史の雄大な構想とともに,原風景に由来する創造活動に意欲を燃やしはじめた昭和30年2月17日,安吾は,脳溢血で急死した。享年49歳。その死にたいする反響は小さく,戦後最大の流行作家にたいするものとして寂しかったが,45年ごろから坂口安吾は,若者たちによって再評価され,大きく復活している。
『定本坂口安吾全集』全13巻(昭42〜46 冬樹社)。
〔白痴〕はくち 短編小説。「新潮」昭和21.6。昭和22.5,中央公論社刊の同名の作品集に収録。戦争末期のさまざまな人間や家畜が同居している裏街の物置小屋のような家に下宿していた伊沢という青年は,部屋に逃げこんできた白痴の女と関係を結ぶ。空襲のもと,肉体だけの女を連れて逃げまわる。せつなさの極みに原質化された人間の姿を発見するこの小説は,2ヶ月前に同じ「新潮」に発表した『堕落論』の小説化として人々に大きな衝撃を与えた。
〔桜の森の満開の下〕さくらのもりのまんかいのした 短編小説。「肉体」昭和22.6。昭和22.5,真光社刊の作品集『いづこへ』に収録。今は花見で人々は桜の下で浮かれるが,昔は桜の下はおそろしいところで人は避けた。満開の桜の森は風もないのにごうごうと風が吹いている。そういう卓抜なエッセイ風の書出しから,鈴鹿峠に棲んでいた山賊が京の美しい姫を略奪し,妻にする。姫はほかの女たちを全部殺させ,わがままのかぎりをつくし,山賊を誘い京に上る。山賊に命じ大納言の若君や名高い白拍子などの首をもってこさせ,まるで人形遊びのように生首で無邪気に無心に遊び興ずる。鈴鹿へ帰る途中,満開の桜の森の下で背負った姫は鬼の姿になって山賊の首を絞める。グロテスクの極致がこの世のものではない美をつくり出した傑作で,民族の深層意識をえぐり,未来的な芸術を暗示している。(奥野健男)
|